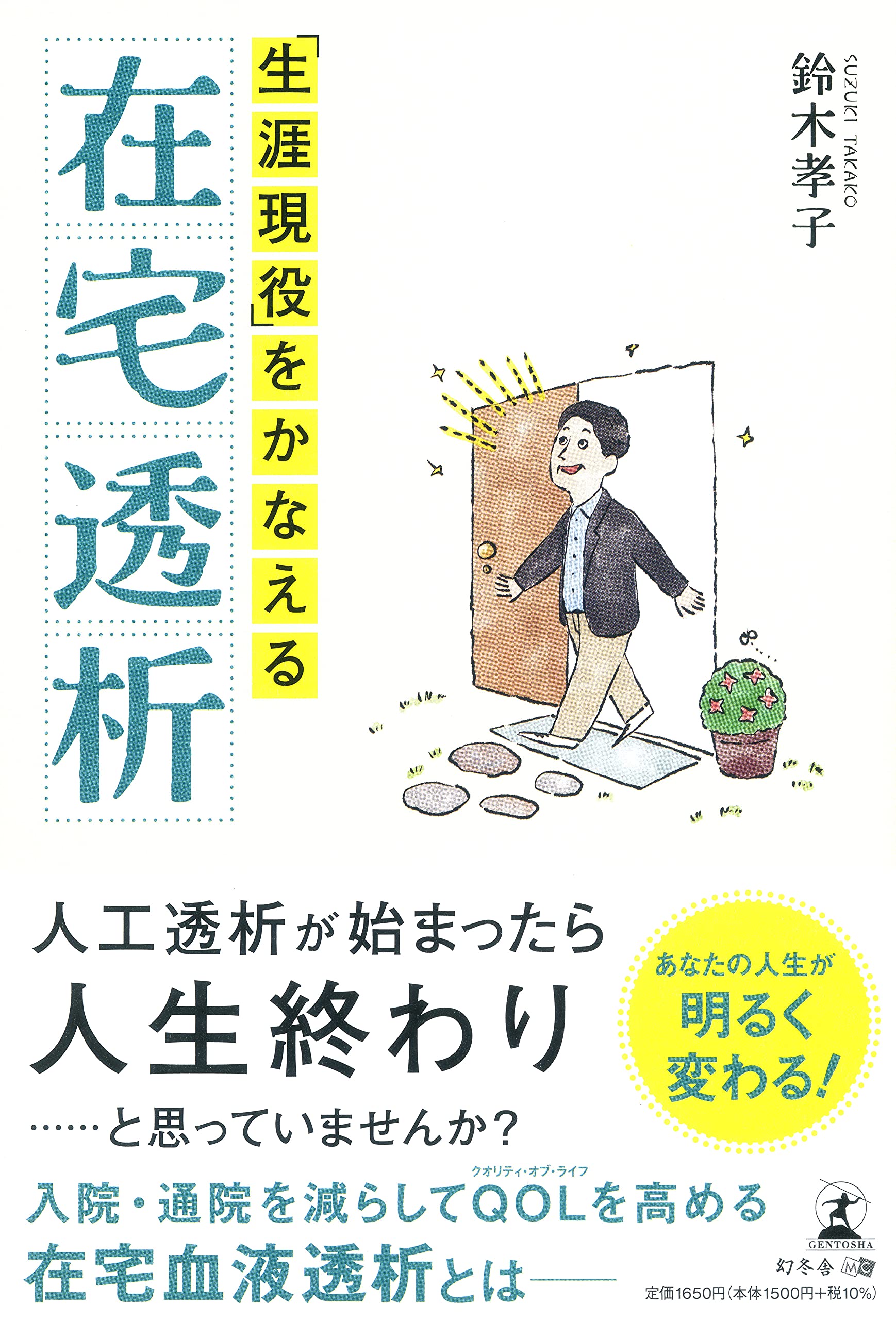[PR]
【著者インタビュー】透析に不安を抱えるすべての人に贈る一冊 腎臓内科専門医が紐解く「在宅透析」の可能性
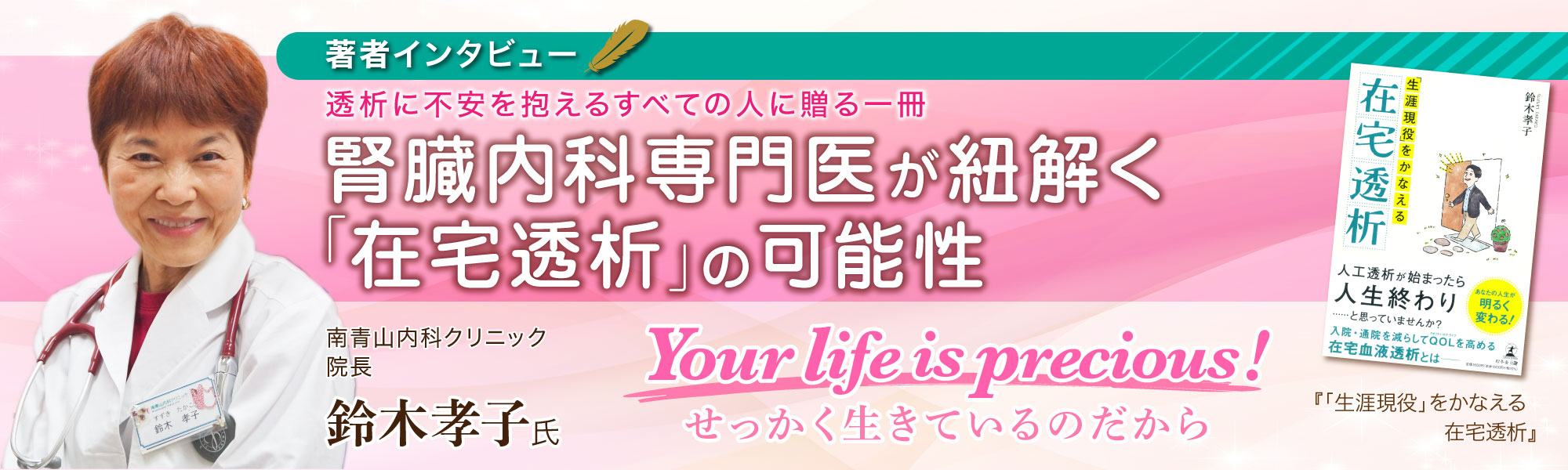
人工透析が始まると、患者さんの生活は一変します。通常週3回・1回4時間の施設透析を行うために、仕事や日常生活のスタイルを変えざるを得なくなります。そのうえ、血圧低下や貧血、だるさといった体調不良に悩まされ、食べたいものも食べられず、透析導入時には絶望する人も少なくありません。 透析患者にとっては「当たり前」であり「仕方ない」と思われてきたQOL(生活の質)の低下ですが、著者の鈴木孝子医師は「透析の方法」や「透析を実施する場所」「透析を行う時間」を工夫することで、患者本人の意志さえあればQOLの維持ができると話します。 透析がスタートしたとしても、前向きに、多幸感を持って生きるためにはどうしたらよいのか、そのノウハウを記した「『生涯現役』を叶える 在宅透析」の刊行に至った思いを、鈴木医師に語っていただきました。
「患者さんのための透析」を実施したいという熱い思い

――本書を刊行されたきっかけを教えてください。
生活に制限を受けることの多い透析患者さんであっても、前向きに意欲的に生きている方がいらっしゃることをすべての人に認知してもらいたと思ったからです。
透析患者さんのほとんどは、透析以前は「当たり前にしてきたこと」の多くを諦めています。職場や家族から「仕事を辞めろ」と言われたり、体調の急変を気にするあまり自ら外の世界をシャットアウトしたりして、社会参加もままならなくなってしまう自分を作り上げてしまう傾向にあります。
実際、多くの施設は限られた診察時間しか透析を受け付けていませんから、わずかな残業もできず会社にいづらくなったという声はよく聞きます。
しかし、私のクリニックで行っている在宅透析や、夜間の就寝中に透析を行う方法を実践されている方は、仕事を減らすことなく、日常生活にもほとんど支障を来すことなく前向きに生活されています。そうした患者さんが特別なのではなく、患者さんの生き方に合わせて施設側が対応すれば、透析をしながら今まで通りの生活を送ることは十分可能だと考えています。
――鈴木先生が提唱されている、自由な時間に透析ができる「在宅血液透析」について教えてください。
患者さんの自宅に透析の機械を設置し、自ら機械操作を行っていただく透析治療を「在宅血液透析」といいます。ここ10年ほどで、在宅血液透析を実践されている患者さんの数は3倍以上と増えてきています。
在宅血液透析のメリットはあげればきりがありませんが、最大のメリットは「自分の自由な時間に透析ができる」ことと、患者さんの多くが口を揃えます。
仕事や趣味の時間を取りづらい、家族や友人との予定に合わせられないなど、時間的制限を受けるストレスは想像を超えるつらさだと思います。その点、在宅血液透析であれば、空いた時間や、就寝時間に合わせて透析を行うことが可能です。
――時間的な問題の解決以外にはどんなメリットがありますか。
体調のコントロールにも在宅血液透析は有効です。実施する日数や時間を主治医と相談しながら調整することで、体調の管理がしやすくなります。4時間以上の長時間透析をすることで体調がよくなるケースは極めて多いと感じています。
また、透析患者さんにとって、食事のコントロールは必須と言われています。透析を行わない日は水分や老廃物、過剰なリンやカリウムを体内に貯めないために食事制限を厳しくする必要があるからです。
しかし、在宅血液透析なら、摂取した水分やカリウム、リン、尿毒素などを、その日のうちに透析で取り除くことが可能ですから食事制限を緩和できます。毎日、透析を実施すれば、カリウムやリンの除去も頻回に除去できますから、リン吸着剤、カリウム吸着剤といった薬の量を減らすことも可能です。
――そのようなメリットの多い、在宅や夜間の透析がかなわない理由は何でしょうか。
在宅透析や夜間透析にはメリットがたくさんありますが、いまだ日本では一般的ではありません。そこには国の保険制度が大きな足かせとなっています。
1回の透析時間を長くし、透析の回数を増やすことで、体調の改善が見込めるというのに、現状の保険制度が適用されるのは「月に14日、1回につき約4時間」と決められているからです。
透析時間については、多少の変動は可能ですが、患者さん一人ひとり、病状は異なりますし、持っている体力にも差があります。ですから、本来は各人に見合った透析の回数や時間を実施するべきなのですが、保険範囲を超えてしまうと、患者さんに自費負担してもらうか、施設側が持ち出しとして経費を被るしかなくなってしまうのです。
在宅や長時間透析や隔日透析で、前向きに生きられるようになった患者たち
――実際に在宅透析を受けている患者さんの声をお聞かせください。
自分で自分の体に向き合える透析
在宅血液透析をされるにあたって、私のクリニックでは約3か月のトレーニングを実施しています。
回路の組み立て方から始まり、機械の仕組み、操作方法、自己穿刺の仕方、透析後の後かたづけまで、覚えることは決して簡単ではありません。しかし、マニュアルに従って実践していただくと思いのほかスムーズに覚えられるようです。
50代の男性患者さんは「準備から片付けまで、生活の一部としてスムーズに透析を行っています。自分で透析をするようになってから、病気についても深く理解するになり、自身の体を今まで以上に知ることができ大切にするようになりました。」と仰っていました。
施設透析で言われるがまま、されるがままの治療を受けるのではなく、自分で自分の体に向き合うことは、治療効果の面でも非常に有効だと考えています。
世の中の役に立てるようになった喜び
30代で透析となった女性患者さんは「それまでの透析では仕事もままならなかったけれど、在宅透析をするようになって体調がよくなりアルバイトができるようになりました。と仰っていました。
国のお世話になって生きているという罪悪感、劣等感でいつも下を向いていた彼女でしたが、仕事をして税金を納められるようになり、少しでも自分が世の中の役に立てるようになったと喜びの声を聞かせてくれています。
患者さん一人ひとりに合わせた「テーラーメイド透析」を目指して
――これからの人工透析はどう変化していくのでしょうか。
自身のクリニックを開院して10年が経ちました。それ以前は雇われ院長でしたから「患者さんに合わせた透析」を実施したくても、理解を得られず断念していました。
ようやく患者さん一人ひとりにマッチした「テーラーメイド」な透析を実践できるようになり、日々、精進しているところです。在宅血液透析だけでなく、夜間透析、土日の透析、また「腹膜透析」も積極的に取り入れています。
腹腔内に透析液を出し入れする口(出口部)をつくり、カテーテルを留置し、チューブをつないで数時間ごとに透析液の入れ替えを行う腹膜透析は、残っている腎機能をより長く維持できる方法です。
患者さんの病状や体調に合わせて、腹膜透析と血液透析を組み合わせた「ハイブリッド透析」を実施するケースもあります。社会生活への影響が少なく、血圧の安定や貧血になりにくいなど優れた透析として注目を集めています。書籍内に詳しい治療方法を著していますので参考にしてもらえればと思います。
――小規模施設ならではの、患者さんに優しい特徴とは?
大きな施設での透析は、どうしても一律の治療になりがちです。水道水をピュアに変換する「RO装置」も数十人で使用することになります。しかし、私たちのクリニックでは二人用のRO装置を使用し、透析液をカスタマイズできるようになっています。
透析に使用するCAPDなどの器具のメーカー選択に関しても、患者さんの希望に合わせたものを取り入れることが可能です。患者さん自身が自分の体と向き合い、治療方法を選択できる。それが透析治療にとってもっとも大切なことだと考えているからです。
Wi-Fi、DVDはもちろん完備していますし、オンライン会議をしていただくこともできます。夜間や長時間の透析にもできる限り対応しています。

透析を受けている患者さんと、心をともにできる生きる医師でありたい
――鈴木先生が透析にあたって大切にしていることはどのようなことでしょうか。
腎臓の病気は「不摂生」が原因だとして非難されることありますが、実際にはそれだけではありません。家族性といって、もともと腎臓の機能が低下しやすい体質の人もいらっしゃいます。透析患者さんが世間から後ろ指をさされるようなことは、決して許されることではありません。
また、60代未満の現役世代が透析を開始するケースも多々あります。そうした人たちが、社会で生きていきやすい環境をつくることも、透析に関わる医師の務めだと認識しています。
――最後に、今後の展望をお聞かせください
高齢になるほど、透析患者さんの割合は増加します。当然ながら、高齢者施設に入所している透析患者さんも多くいらっしゃいます。そうした方たちに腹膜透析やハイブリッド透析を実施できると体への負担を軽減できますし、透析による保険金額を抑えることもできます。
介護士や看護師の力を借りながら、高齢者施設での新たな透析の手法も開拓していきたいと思っています。
また、私自身、透析患者さんたちから多くのことを学ばせていただいています。透析が必要になっても「自分の人生を前向きに生きたい」と望む方たちの熱い思いは、私がテーラーメイド透析を実践するための大きな原動力です。
透析をスタートして2~3年経過すると、「自由に時間を使えない」「社会参加できない」こと当然のように受け入れてしまう患者さんが多くいらっしゃいますが、人生をもう一度楽しむために、治療方法を改めて考え直す機会を持ってほしいと願っています。
そして、在宅血液透析・腹膜透析やハイブリッド透析・腎移植など、ご自身にフィットする透析を含めた腎代替療法を考え直し、一歩踏み出す勇気を持ってもらえたら、私たち医師も全力で支えてまいりたいと思っています。
南青山内科クリニック 公式サイト