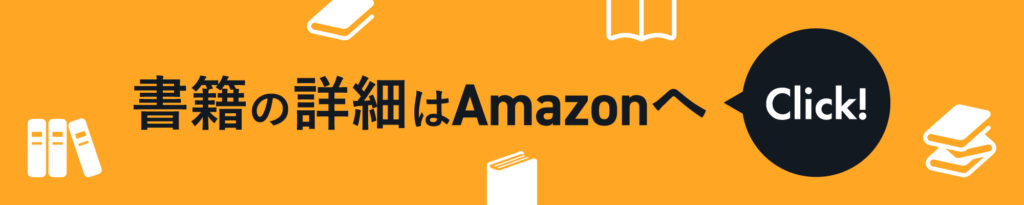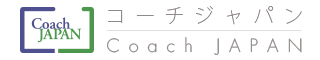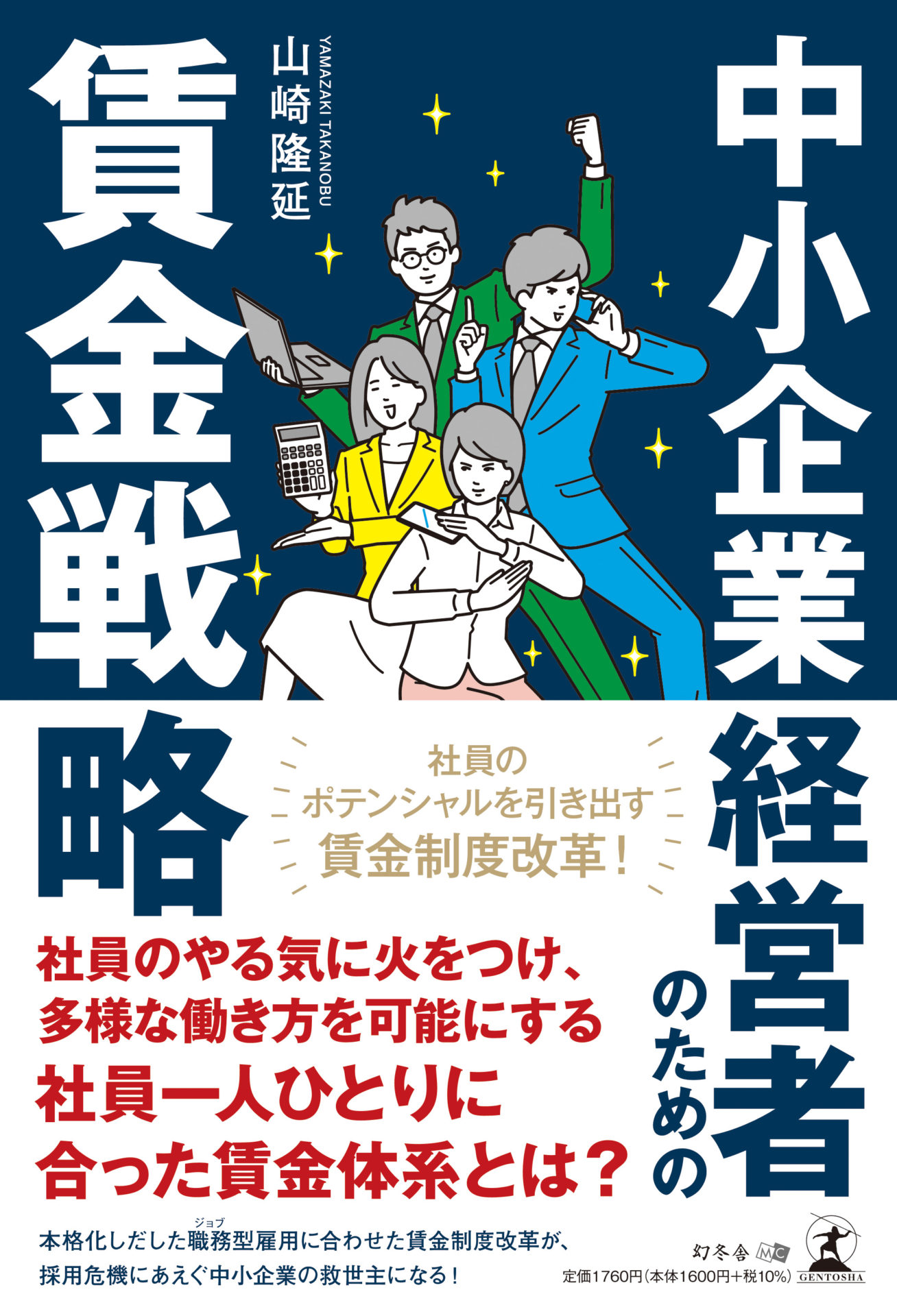[PR]
【著者インタビュー】超人材難の時代に中小企業の生き残りをかけた人材戦略とは
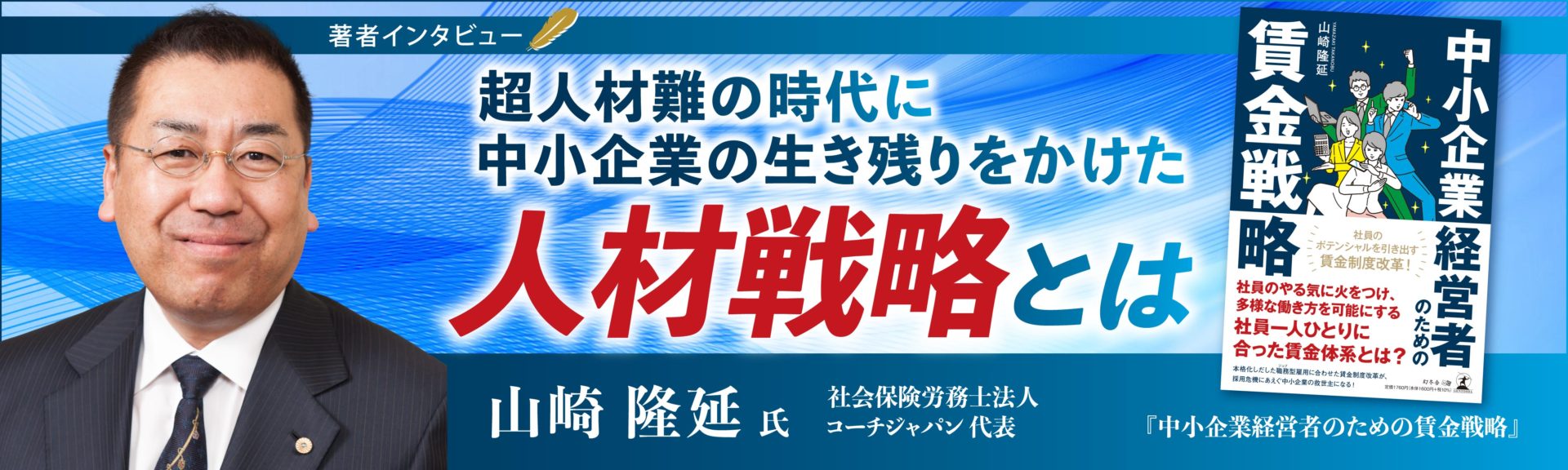
現在、労働市場はこれまでの終身雇用を中心とした「メンバーシップ型雇用」(職能給)から「ジョブ型雇用」(職務給)へと移行しつつあります。そのようななか、人材確保において苦境を強いられる中小企業は、今いる従業員一人ひとりを大切にし、賃金体系や評価制度を見直すことで、この変革の時代を飛躍のチャンスにすることもできるかもしれないのです。 そこで、45年以上にわたり中小企業経営のサポートに従事し、全国680社以上の顧問企業を抱える社会保険労務士法人コーチジャパン代表であり、著書『中小企業経営者のための賃金戦略』を刊行した山崎隆延氏に、中小企業が取り組むべき課題や人材流出を防ぐポイントについてお聞きしました。
ヒトを資本の一つとして重視し、“人財”の流出を防ぐ

――著書『中小企業経営者のための賃金戦略』刊行に至る背景をお聞かせいただけますか?
今こそ日本の労働市場の変革のタイミングであるから、ということになるでしょうか。昨年2022年9月、岸田内閣総理大臣が訪米し、ニューヨーク証券取引所でスピーチを行った際に日本の優先課題を挙げ、その中の1つとして「ジョブ型雇用への移行」に触れたのです。そして帰国後の国会でもこれまでの「職能給」から「職務給」(ジョブ型)への転換が必要であることをあらためて表明しました。
“ヒト”を資本としてとらえ、その価値を重視する「人的資本経営」が広がる中で、そのための情報開示のガイドラインとなる国際標準化機構(ISO)の「ISO30414」への対応がポイントになりますが、日本ではあまり進んでいませんでした。
実は私どもでは、2018年頃の時点でこの先を見据えて「人的資産報告書」という用語の商標登録をしていました。そこには「決算書のベースにあるものこそ人だ」という思いがあったのですが、現実的に運用するには数値化が十分にクリアできていなかったのです。
しかし現在では、「ISO30414」の指標の数値計算を踏まえたことで、いよいよ中小企業においても賃金体系や評価制度の見直しに取り組むべき時期がきたといえます。
――とくに中小企業の人材戦略に焦点を当てているということですね。
今年から「人的資本」の情報開示が義務づけられました。項目でいうと女性管理職の比率や男性の育児休暇取得率、男女間の賃金格差などがありますが、そのルールが適用されるのはあくまでも一定の上場企業です。しかし、だからといって中小企業はまったく無関係とはいえません。
2023年は賃上げムードが高まり、大企業を中心に多くの企業が賃上げを発表する一方、中小企業のほとんどは最低賃金が上がるだけでも大変な思いをしています。
それでも、なんとかして賃上げを実現しなければいけないと思っているのに、手塩にかけて育ててきた人材が大企業に引き抜かれてしまったり、補充のために求人を出しても人が集まらず、人材不足は深刻な状況です。
まさに喫緊の課題といえる人材戦略で、欠かすことのできない“人財”をしっかりと確保し、可能な限り流出させないルール作りをしましょうということなんです。
ジョブ型雇用の導入は従業員の全員でなくてよい。そして導入すれば夢の実現につながる。

――中小企業ならではの取り組みとはどのようなものでしょうか。
ジョブ型雇用の導入に取り組もうとするとき、「職務記述書」を作ることから考えがちですが、大企業の場合と、現時点で情報開示が義務ではない中小企業では、対応のしかたがまったく異なります。
中小企業の場合、そもそも従業員全員にジョブ型雇用を導入する必要はありません。ですから面談で本人の希望も聞き入れ、双方の合意の上で導入を進めます。それでこそモチベーションも上がりますし、個人の夢を育むことにもつながるわけです。それができるのは中小企業だからこそ、といえます。
――ジョブ型雇用を導入する人と、しない人がいるのですね。
従業員個人の志向や現状から、3つのタイプに分類して見究めることを勧めています。
まず、「期待人財」は能力も意欲も高く、本人も会社から期待されていることを理解している人です。しかし、条件次第では流出しやすい場合もあり、ジョブ型雇用を取り入れることで手厚い賃金体系を導入したい人です。
次の「高度安定人財」は期待人財に次ぐ存在です。スキルは高いですが、子育てや介護、結婚の予定があるなど、さまざまな事情で今はそのときではないという人です。
そして、最も多い「安定人財」は、ミスやトラブルもなく、現状維持を希望するようなタイプですが、こうした社員さんたちが日々の業務の多くを支えているのも事実です。ここにあてはまる人には、急いでジョブ型雇用を導入する必要はないと考えてよいでしょう。
こうして分類するのは何も査定や評価を行うためではなく、よりよい働き方を選択するためです。忘れてはいけないのは、全員が企業にとって欠かせない人財で、必要でない人は誰もいないのです。
――ジョブ型雇用を進めるに当たって、研修や教育も必要ですね。
かつて、研修や評価等を一律に導入した時代には、それを負担に感じる人もいたわけです。もちろん必要があってのことでしたが、無理に導入しても従業員のやる気を失わせてしまったり、反発を招くことにもなりかねません。
重要なのはやはり一人ひとりとていねいに話しをし、企業側で研修・教育にかかる費用を確保して、「人を育てる」意識をもつ必要があります。しかもそれは10年単位などの長いスパンでみる必要があります。
昨今、「リスキリング」という言葉が浸透していますが、業務向上にはスキルアップがかかせません。
そこで経営者側には、売り上げのうち一定の割合を必ず研修費に充てるべきだと言っています。美容室を経営するある企業では、売り上げの3%を研修費にあて、パリ・ニューヨークへの留学を含めたキャリアアッププログラムを取り入れています。
プログラムの内容は企業によってさまざまですが、いずれにしても幅広いメニューを企業側で用意し、それも先ほどの分類により、期待人財の人には多めに、安定人財の人には少しゆるめにといったメリハリをつけて取り入れるのです。「今いる人たちにお金をかける」という観点で、研修に費用はあらかじめ確保しておくことです。
労働者と経営者はお互い様で取り組む必要がある
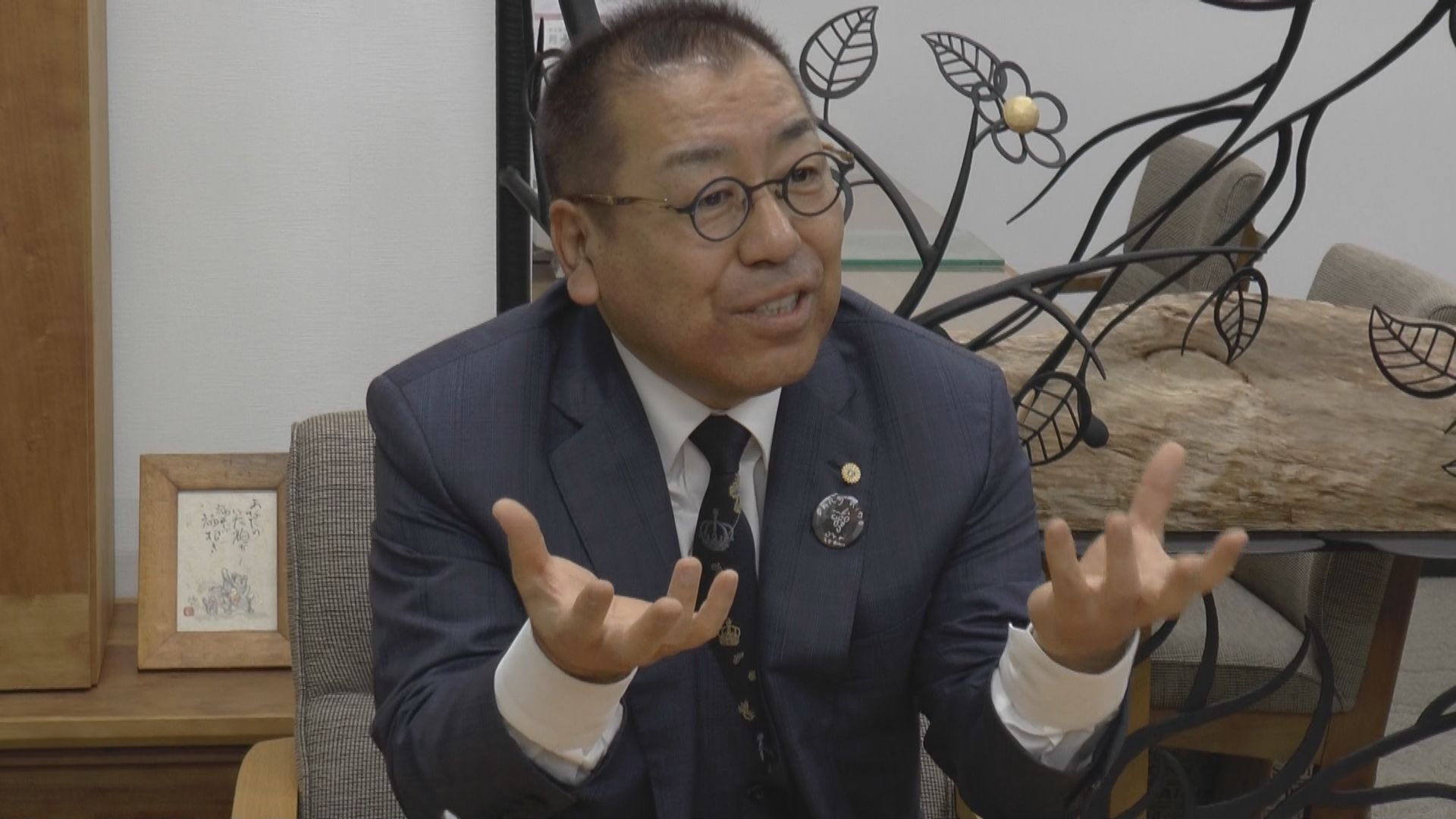
――賃金体系も一人ひとり異なるのですね。
私どもが推奨する中小企業版のジョブ型雇用の導入では、従業員本人ときめこまやかに面談をし、話し合いによって最終的に一人一人の賃金規定を決めます。そうするとやる気も高まりますし、不要な残業も減っていくでしょう。副業に関しても前向きに考えていくべきです。
ただし、そこに至るにはやはり評価のしくみも重要になってきます。「コンピテンシー」とは特定の業務や役割で突出した成果を出し続ける行動特性で、「エンゲージメント」は愛着心や信頼関係を表しますが、両者のスコアを掛け合わせて、その人のいいところを抽出して評価することができます。
人は意外な能力や趣味など、企業側では知らなかった一面をもっているもので、そうした面を引き出すと、会社にとって新たな事業のヒントになることもありますし、現状を打開する大きなチャンスになることでしょう。
人の力を信じ、人財力を経営に活かす。社会保険労務士は法律の伴走者に
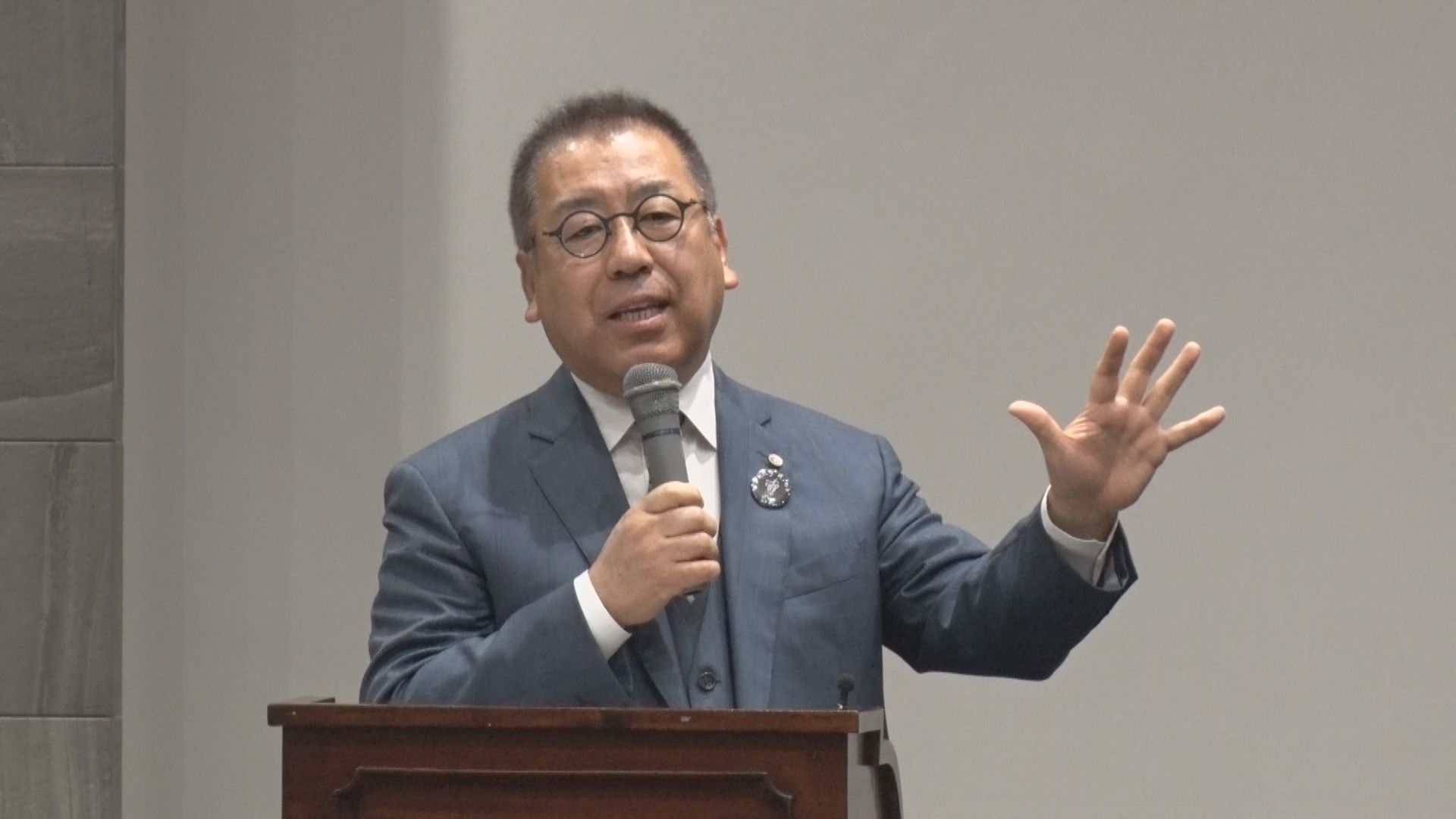
――社会保険労務士とはどんな存在ですか?
法律がわかって、なおかつ人の気持ちがわかる、そんな存在ではないでしょうか。法律の伴走者ともいえますし、そうありたいと考えています。
少し大きい話になりますが、就業規則のある箇所にぜひ注目していただきたいんです。それは就業規則の第1条 第1項で、そこに就業規則の目的が2つ書いてあります。
まず1つは「法律を守る」ということ。近年とみに重要視されるコンプライアンスであり、それもあって社会保険労務士の95%が法律変更のための相談業務がメインの仕事だと思っています。
実は就業規則の第1条のもう1つにあるのが「職場秩序の維持」です。ジョブ型雇用や賃金体系もここにかかわってくるでしょうし、働きやすい環境づくりからウェルビーイングを実現することが今こそ求められています。そのためにも、社会保険労務士は戦略的な思考をもつべきであると考えています。
――最後に、中小企業の経営者、企業の人事担当者様を含め、人材戦略に携わる人にメッセージをお願いします。
従業員と経営者は50対50、お互い様であるという意識をもち、共感性をもって取り組むことです。それでこそよりよい状態、ウェルビーイングな労働環境を実現できるのではないかと思います。
人的資本経営を重視し、一部のジョブ型雇用を強くしていくメリットには、「人がチームに変わっていく」ことがありますし、中小企業こそ実現できると思いますし、ぜひそこに気づいてもらえたらと思っています。