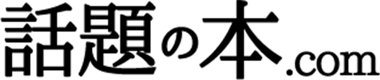究極の愛と選択を描いた衝撃のデビュー作『マリアライカヴァージン+』。インタビューの前半では、ジェンダーの問題や作品や登場人物にまつわる思い、読者に向けたメッセージを伺いました。
後半では作者である内藤織部氏自身と、『マリアライカヴァージン+』の裏話、そして今後について明かして下さいます。
たとえ重いテーマでも自分なりにポップに書き綴りたい。ふとした瞬間に浮かんだアイデアを作品として結晶化する
――小説執筆に興味を持たれたきっかけを教えて下さい。
子どもの頃から本ばかり読んでいて、物語を書いていたのは小学生の頃からです。絵本に始まり、思春期には太宰治に夢中でした。
学生時代は文学部で、毎日のように小説を書いていました。クラスメイトはわりと暗い内容が多かったですが、私はいろんなジャンルで、テーマ自体は重たいものも書くのですが、重くてもポップに書きたいですね。
学生の頃に耳にしたある小説家の言葉が忘れられません。それは「明日がある小説を私は書きたい」「私が死んだら、そういうことを書いてくれる作家が出たらいい、明日が元気になっていくような、浄化されるような」と。それが自分の中にずっとあり、『マリアライカヴァージン+』も希望を感じる話にしたいと思いました。
――執筆スタイルはどのようなものでしょうか。
午前中5時間ほど集中して書くことが多いです。それで力尽きる感じ。書くときは、物語の流れはそれほど決めず、思ったことをどんどん書いていきます。登場人物たちが頭の中で勝手にしゃべりだすので、それをキャッチして綴るのです。
私は、普段からわりと、物事を俯瞰して見ているようなところがあり、人が言った言葉、胸に突き刺さった言葉をよく覚えているほう。人と何を食べたか、どんな雰囲気だったか、その人が来ていた服も。それは特技というか、作品にも活かされているのかもしれません。
――行き詰まってしまうこともあるのでしょうか?
進みが悪かったり、手が止まってしまうときは、本を読んだりすると、そこから想起されたりして、書き続けられたりします。そのとき書いているものと近い内容のものは避けて、好きなミステリ小説を読んだりするとリフレッシュできます。
さらに行き詰まったら、旅にでます。ただじっとしているよりも、動いているとき、新幹線に乗っているときなどにアイデアが浮かびやすいですね。
ボーっとしながら、窓から流れる風景を見ていると、ふとした拍子にあのときこんなことがあったなということが映像で思い出されて、それがつながって、これを小説にしたらいいのではと思いついたりします。
モデルとなる人物もいるが、物語にあわせてアレンジして唯一無二の存在に仕上げる
――物語のキャラクターたちにはモデルがいるものでしょうか。
自分を投影することはなくて、キャラクターのほとんどは創作だったり、印象的な人をミックスしたり、物語にあわせてアレンジしたりします。
今までの小説では誰かをモデルにしたことはなかったのですが、今回でいうとマリアや婆には元となるモデルがいます。といっても、特定の人をそのまま書いているわけではありません。
主にビジュアル面から入って、物語に合わせてさまざまな脚色をしますが、やはりポイントやキーワードがあるので、その人のコアなファンの人がみたら、もしかしたらわかるかもしれませんね。
実は婆の家も、麻布十番にあった三味線の家元のご自宅。今はもう再開発の憂き目にあってなくなりましたが、黒塀に冠木門、松の枝がそびえていて。中に入ると磨き上げられた飴色の廊下がある花柳界の粋なたたずまいでした。モデルとなった家元も、本当に素敵な方でした。
――『マリアライカヴァージン+』の刊行が決まったタイミングでお会いになった人がいらっしゃるそうですね。
はい。太宰治の娘である太田治子さんに久しぶりにお会いしました。
そのときにかけていただいた言葉がとても心に染みるものでした。ゆっくりと優しく、温かい口調で、「嘘のない、ごまかしのない文を書きなさいね、息の長い書き手さんになりなさい」「上手に書こうなんて思わなくていい」という言葉をかけて頂きました。私の中でより執筆に対する思いが強まりましたね。
太田治子さんは繊細で、シャイで、それでいて強い芯がある女性です。そんな彼女の目からみた「父・太宰治」を題材に書いてみたい、という思いもずっと心に温めています。
物語の中には、おもちゃ箱みたいにいろんな仕掛けを用意しています
――この小説には遊び心にあふれた仕掛けがいろいろありますね。
たくさんの仕掛けを物語の中に閉じ込めました。
例えば、みちるの母は可愛らしい人で、娘にお弁当を渡すときにクイズのような問いかけをしたりします。そんな母が亡くなり、みちるは母をもとめてさまよいながら、制服の赤いリボンをつかんで「ブルーのマントに赤のドレスを着た女性はだーれだ」と呼びかける場面があります。みちるにとっては切実なシーンですが、これはわかる人にはわかる。
――その解釈は読む人にゆだねる感じでしょうか。
そうですね。ほかにもあって、たとえばみちるは冒頭で目を覚まし、ラストで目を閉じる。もしかして、これはみちるの夢の話か、あるいは妄想だったのかと捉えることも。まるで一夜の夢のように。作者が言うのも何なのですが、いろんな解釈をして楽しむことができると思います。
ラストシーンは、視点がパッとかわってある人物が登場します。それは一体どんな存在なのか、何の意味があるのか、それも楽しみながら考えてもらいたいですね。
小説は作者だけのものではありません。書いた後は読んだ方のものだから、どのように捉えてもらってもいいと思いますし、広がりを感じられるものを書いていきたいです。
言葉を通して読者とつながることは神秘的なこと。小説は絶対に滅びない
――小説を書くことは内藤さんにとってどのようなものでしょうか。
一言でいうなら、カタルシス。自己満足だけではないし、悩んでいる方のためというわけでもありません。大上段に構えず、自分のもとにふっと物語がくるからそれを書いておこう、というくらいの気持ち。それも自分の浄化といえばそうなるでしょう。
こうしたらキレイな物語になるな、あるいは残酷な物語になるなと思ったり、最初の一行が浮かべばいける、という感覚になります。
物語を書いて世の中に出すなんて、究極としては自己中心的なこと。ミステリ作家のアンソニー・ホロヴィッツも大好きですが、近作の『ヨルガオ殺人事件』に、作家なんていうものは自分にしか意識が向いていない、という一節があり、そこは共感するところです。
しかし、言葉を通して顔も知らない誰かとつながっているのは本当にうれしいこと。私が書いたマリアのイメージが読者に届いて、その思いが宇宙に浮遊していると思うと、不思議な気持ちになります。なんて神秘的だろうと。
それはとてもありがたいことですし、そういう気持ちがなくなったら、書いてはいけない。読者がいてくださるのは心強いし、絶対に小説は滅びないと思いますね。
――今後の執筆活動についてお聞かせ下さい。
これからということでいえば、華美でない、奇をてらっていない文章を綴っていきたい。特にジャンルも決めていませんし、思いっきりジョークのきいたものも書きたいですし、構想はいろいろ。
実はこの作品を執筆していたときに、愛犬の看病をしていました。体調の良いときには、よく犬と一緒に有栖川公園を散歩していて、愛犬は走るのが好きだったのですが、走ると失神してしまう。そうなると私はあわてて蘇生するというのをたびたび繰り返して、でも結局亡くなってしまいました。
母のときと同じように、私はやはりショックを受けて、いまだに有栖川公園に足を踏み入れられないほど。ペットロスと言われますがペットは家族と同様で、愛するものを失ってそこから立ち直ることができない方が多数いると聞きます。
そんなことがあって、今(取材当時)はペットと命をテーマにした物語を書いています。これも自分にとって書くのがつらい題材でありつつ、書きたいと思える物語です。
生きたいように生きればいい。誰もが必ず幸せになれると伝えたい
――次回作も進んでいるのですね。最後にメッセージをお願いします。
まずはデビュー作となる『マリアライカヴァージン+』をぜひ読んでいただきたい。いろんな年代の人が、いろんな愛に決着をつけていく物語ですし、生きることに通じています。
そして、これからいろんな物語を書いていきたい。私に書けるのだろうか、と不安になることもありますが、真摯にブラッシュアップしていくしかないと思います。ときに現代の闇につながる題材でも、私らしい切り口でやっていきたいと思います。
みちるや婆は決して自分の望み通りの人生を送ってきたわけではありません。それでも、生きたいように生きている、そこには打算もないし、我慢もありません。
すべての人生には“抜け道”がある、と言いたい。何かに悩んだとしても、絶望する前に必ず「道がある」ことを伝えたいと思います。
小学生や中学生が自殺をする報道がありますよね。死を選ぶほど嫌なら学校なんか行かなくてもいい。自分が生きやすいようにカスタマイズして生きればいい。人生に正解はなくて、あなたが選んだものが正解。そう思えば、必ず幸せになれる方法があるはずです。
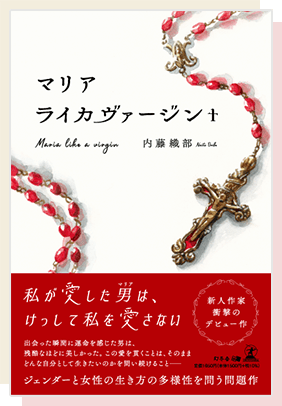
ジェンダーと女性の生き方の多様性を問う問題作
私が愛した男(マリア)は、
けっして私を愛さない
出会った瞬間に運命を感じた男は、残酷なほどに美しかった。
この愛を貫くことは、そのまま
どんな自分として生きたいのかを問い続けること――
<新人作家 衝撃のデビュー作>