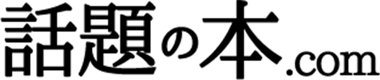「私が愛した男 マリアは、けっして私を愛さない」
究極の愛と選択を描いた衝撃のデビュー作『マリアライカヴァージン+』。
大学生のみちるは、ある雪の日に偶然マリアと出会います。切れ長の茶色の瞳をもつ孤高のギタリストであるマリアに、知れば知るほど惹かれていくみちる。
けれど、手を伸ばせば触れられるほど近づいても、愛は手には入らない……。
そしてみちるは、人生をかけた大きな決断をします。
作者である内藤織部さんに、著書に込めた思いと愛すべきキャラクターたち、そしてこれからについて2回に分けて伺いました。
究極の愛について書いてみたかった。無垢で、美しい愛の決着をどうつけるか
――デビュー作『マリアライカヴァージン+』刊行のきっかけがあればお聞かせ下さい。
最初にこの作品を書いたのは10年前でした。書きためていたものがいくつかあった中で、小説家としてのデビューが決まり、担当編集者の勧めもあって選んだのがこの作品。
10年も経つと、その間に社会的な変化がいろいろあるので、時代に合わせてマニキュアはネイルに、携帯はスマホに変えたりしました。
しかし、本作の中で非常に重要な部分だとわかっていながら、正面から向き合い切れていなかった箇所がありました。それは作者である自分にとって一番つらい、触れたくないところだったのですが、そんなためらいというか、臆病になっていた部分を編集者にはやはり見透かされてしまいました。
でも背中を押してもらったことで書き切ることができて、最後のパズルが完成したと思いましたね。
――どれはどんな箇所なのか、お聞きしてもよろしいですか?
それはみちると母との関係、大好きな母の死についてなのですが、みちるが心の奥に秘めている母への思いはこの作品で核となる大切なところです。喪失感や母との別れをきちんと掘り下げないと、みちるがマリアに向ける強い愛情もぼやけてしまいます。
みちるは母の思い出に浸り、捨て鉢な行動を取ろうとしますが、父と二人で生きていくために「母の思い出につながる場所は目を閉じるのだ」と、心を閉ざそうとします。
本作は私小説ではありませんが、私自身が母に対してそう思っていました。実は恥ずかしながら母の写真もまだ見られないほど。この小説には、誰もがもっている母親に対する思いを込めているといってもいいかもしれません。
――『マリアライカヴァージン+』にはいろんな愛のかたちがありますね。
さまざまな小説を書いてきましたが、意外と恋愛の話は少なく。でも一本くらい、純愛の物語、それも「究極の愛」について書いてみたいと思いました。
誰かを好きになるとき、受け入れてもらえる相手を選んで恋に落ちるわけではありません。思いが成就しないこともあるでしょう。でも、異性との間であればフラれたとしても、それなりに相手を受け止めていることになるでしょう。
ですが、好きになった相手が女性を愛さない人だったら、それを撥ねつけるしかなくなる。迷うこともないし、一瞬たりとも受け止めてもらえない。それはとても残酷なこと。
そこから究極の愛とはどんなものだろうと考え、そんなときはどういうふうに自分の気持ちに決着をつけるのだろうと考えました。
――究極の愛は美しく、そして残酷でもありますね。
私が描きたかったのは、完全なるイノセント、究極に無垢な愛情。そして美しいものにしたいと思いました。美しさは容赦がない。ときに残酷なほどです。
私は映画も好きでよく見ていますが、最初に美について深く学ばせてくれたのは、ルキノ・ヴィスコンティ監督の世界観。トーマス・マン原作の『ヴェニスに死す』を初めて見たのは中学生のときでした。
子ども心に、なんだこの美しさは、と思い、衝撃を受けました。ラストシーンで夕日を見上げる少年がいて、それを眺めながら男が亡くなっていく。非常に美しく、深い余韻を感じさせる作品でした。
人を愛することはときに狂気をはらむこともあります。日本でも、恋しい人に会いたい一心で放火をする「八百屋お七」の話などがありますが、それもとても純粋で無垢な愛情といえるのかもしれません。
セクシャリティの違いは当たり前のことで、なにも特別なことじゃない
――マリアはゲイですが、LGBTQ+やジェンダーの問題などにも関心がおありでしょうか。
この作品を書いたのは10年前だと言いましたが、LGBTQ+やジェンダーの問題は以前からありますし、むしろそれにこだわるのは古いのではないかと私は思っていました。
ですが、六本木 蔦屋書店がリニューアルオープンしたとき、メインの棚にどのようなジャンルの本を並べるのだろうと興味を持って見に行ったところ、世界中のジェンダーの本がズラリと並んでいました。知人を通して「これは古いのでは?」と聞いたのですが、「いや、今なんだ」と。
「LGBTQ+」という言葉が広く浸透し始めたのも近年のことですが、それを扱う作品は昔からありました。でも、これが10年前だったらマスコミが取り上げなかった。
それで、この本を今出すことに意味があるのだと納得しました。
――内藤さんのまわりではLGBTQ+は特別なことではなかったのですね。
子どもの頃、生家がレストランをしていました。壁にフランス帰りの画家が描いた絵があり、照明が暗めで落ち着いた雰囲気で、来店されるお客様が母のことをマダムと呼んでいました。
当時、お客様の一人にとても美しく、男性か女性かわからない方がよく来ていました。今思えばその人はトランスジェンダーの方でしたね。
当時は今よりもっと認知されていなかったので、外に出ればやはり奇異な目で見られます。でもその人はそんなことはまったく意に介さず、常にすっくと立っていました。それが子ども心にとてもカッコよく見えたのを覚えており、幼い私に慈悲深い微笑みをいつも向けてくれたことを今でも覚えています。
その方以外でも、セクシュアリティの問題で苦しむ人は、男の気持ちも女の気持ちもわかる魅力的な方が多いと感じます。なので、この物語は彼らのような方々へのオマージュでもあります。
日本の「LGBTQ+」に対する理解や対応はまだまだ遅れています。
セクシュアリティの問題は身体上で起こる細胞レベルの問題でしかありません。右か左かの違いにすぎません。決して特別なことではありません。歯がゆい思いになりますが、たとえ理解できなくても尊重すべきですし、もっと当たり前のことになったら、「LGBTQ+」なんて言葉もなくなると思います。
すべてのキャラクターは命をもっていきいきと存在している
――この物語では、マリアにとても存在感が際立っています。
マリアはとても美しい男ですが、外見上の美しさだけでなく、そこはかとない哀しさも秘めていて、自分の美意識が完璧に確立されています。他者に対して「人なんていらない」くらいに思っているでしょう。
そこには生い立ちも関わっていますね。マリアはずっと孤独に生きてきたので、人への愛情の示し方がよくわからないのかもしれません。
ですが、物語の中にはマリアが認めた人も登場します。それがどんな人なのかは、作中で出会っていただきたいのですが、一方でマリアはみちるのことを妹のように思い、情もあり、深く理解しています。でも寂しい男なのですよ。
マリアくらい思いを込めたキャラクターはいなくて、最後のゲラを託したとき、ああ、これでもう手を入れなくていいのだと思うと寂しかったですね。マリアのほかにも登場人物たち全員に対して幸せになってほしい気持ちです。
―― 女性キャラクターたちはみんな強いですね。
一般的に女性が虐げられてきた歴史があったとしても、決して弱い存在だとは思わない。女性は強かったからこそ、力を振るいたがる男たちを支えられたのかもしれません。特に明治の女性たちは気骨のある女性が多いですね。矜持を持ち、底力を示してきたのは女性です。
マリアを引き取った婆も強い女性。ままならない過去を抱え、二度と子どもを育てることはしないと思っていたものの、高齢にさしかかってもう一度生きてみたいと思って孤児院にいた幼いマリアをもらうという選択をしたのです。たくましいですね。
――『マリアライカヴァージン+』には今後の展望もあるそうですね?
来年の夏頃に漫画化される予定です。この物語は、もう自分の手を離れていったん完成しているので、それぞれのキャラクターが一体どのように描かれるのか、私自身とても楽しみにしています。
この物語にはモブキャラはいないくらい、全員がいきいきと存在しています。むしろ自由奔放すぎる。それで私は、「ちょっとキャラが立ちすぎではないですか」と聞いたほどですが、「だからこそ漫画になるんです」といわれましたね。
――そして終盤、みちるの“選択”にはとても驚かされました。
みちるなりの愛の表現といえると思います。決して思いつきや衝動ではない。
みちるは“抜け道”といっても、自ら“けもの道”を選んだように見えるかもしれません。でも、それは彼女が納得した生き方で、彼女なりに一番幸せに近い選択。
この物語では、誰かが誰かに恋をしてまるでメリーゴーランドのようにかけめぐっています。
みちるも、婆も、愛にそれぞれの決着をつけています。それをみてほしい。報われない愛、叶えられない愛、そして続行中の愛に自分なりの納得の仕方、とらえ方があるのです。愛の形は決してひとつではありません。
みちるたちの生き方を見て絵空事だと思う人は、それを絵空事だといえる人生を送っているということ。小説は教科書ではないのですから、何を思ってもかまいません。
こういう愛し方でもいいのかと思ってもいいし、批判でもいい、何か一言でも読者の方の心に残ったら嬉しいと思います。考えてほしいというより、感じてほしい。それが一番です。
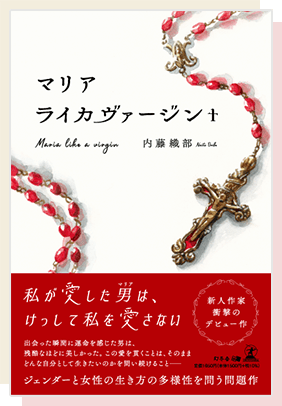
ジェンダーと女性の生き方の多様性を問う問題作
私が愛した男(マリア)は、
けっして私を愛さない
出会った瞬間に運命を感じた男は、残酷なほどに美しかった。
この愛を貫くことは、そのまま
どんな自分として生きたいのかを問い続けること――
<新人作家 衝撃のデビュー作>