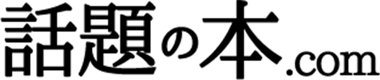マリアの本当の記憶は、孤児院で過ごしていた日々から始まる。
そこにはサンタ神父と呼ばれる院長がいた。ひげが顎から耳のまわりまでサンタのように生えている。クリスマス会になるとサンタクロースの衣装をつけ、段ボールでできたトナカイとそりに座り、子どもたちにプレゼントを渡す。小さな祭壇の前に子どもたちは一列に並び、自分の順番がくるのを照れくさそうに待っていた。
順番がくるとマリア像を通りすぎて神父の前に立ち両手をひろげると、真っ赤な包装紙に緑色のリボンで結んである箱がのせられる。プレゼントは全員一緒のものだった。色鉛筆だったり、チョコレートだったり、手帳だったり、みな使用して消えていくものだった。
マリアは、7歳のときにもらったポストカードが嬉しかった。幾重にも重なったレースのドレスを着ている巻き髪の少女、セピア色の時間に閉じこめられた西洋の少女の一枚の写真は、衝撃だった。その少女に生まれ変わりたいと強く思った。それが、自分がうっすらと感じていた疑問の答えだった。
ビスケットとミルクの香り。オルガンのきしむ音。聖書の紙の冷たさ。両手に乗せられたプレゼントの重み。今でもマリアはギターを弾いていると孤児院の風景が頭をよぎる。
学校から帰ると女の子たちは、宿題をすませ中庭に集まる。風呂敷や帽子、シーツなどをもちよりお姫様ごっこが始まるのだ。マリアは決まって王子役にされた。白いタイツを履き、バルーンのような短いスカートをはかされる。金色の包装紙で作った王冠は、ときどき新聞紙になったりする。マリアはそれが嫌で、王冠にビーズやビー玉をセメダインではりつけた。女の子たちはマリアの器用さに驚いていた。
次の日から、女の子たちは部屋から布切れを持ってきては、自分のつたないドレスのデザインを見せ、マリアに作らせた。はじめはセメダインで布地をくっつけていたが、匂いが嫌だと女の子は抗議し、針と糸をマリアに押し付けた。マリアは自分の王子のブラウスのデザインは手直しをして仕上げた。頭のなかで考えたことが現実に目の前に現れることの喜びを感じた。王子の服装をしたマリアがペタンと廊下に座り、針に糸を通す姿は、神父や台所のおばさんたちに頬笑みをもたらした。けれど中学生の勇気君が学校から帰ってくると、女の子たちは勇気君を王子にする。10歳のマリアは勇気君を見ると嬉しかった。彼が王子で自分がその姫ならどんなに誇らしいかと思った。だいいち、名前がいいじゃないか、勇気君。ソシテオレノナハステオ。
マリアは生後3ヵ月で捨てられた。
孤児院の門前にはとてつもなく大きなポストがあった。ドラム缶を横にしたような形で、ルルドの泉、と名前が書いてあった。ある日、朝の散歩から帰ったサンタ神父が、ポストの下で段ボールを見つけた。箱のなかには、やっと首のすわりかけた赤ん坊がいた。指しゃぶりに夢中で、サンタ神父が抱き上げると泣き出した。
「ごめんね。邪魔しちゃって」
人生最初に聞く他人の言葉としては、上出来のうちだろう。段ボールのなかには真っ赤な毛布とヘビのぬいぐるみがあり、「私はこの子を育てる気持ちになりません。どうぞよろしくお願いします」とヘビの首にメモがくくりつけてあった。
サンタ神父は泣いている赤ん坊の顔をのぞきこんだ。まだ3ヵ月くらいだというのに顔立ちははっきりとしていた。髪の毛の量も多く、くっきりとした茶色の目に濡れたまつ毛が光っていた。
勇気君が学校から帰ってくると、いつものように鞄を机に置き服を着替えようとタンスを開けたときチーズとミルクを混ぜたような匂いがした。匂いのするほうに目を向けるとベッドの蒲団から小さな黒いものが動いていた。そばによると、こちらの気配に気づいたのかゆっくりと頭を動かしこちらを見た。ミルクを吸うように唇をすぼめている。勇気君はサンタ神父の部屋にかけていった。
「父さん、赤ん坊はどこから来たの?」
「玄関のポストの下に置いてあった」
「かわいそうに。なんてことするんだ」
いろんな事情で子どもたちはルルドの泉に預けられるが、捨て子ははじめてだった。
「名前はあるのかな?」
「手紙にはステオとあったけどね」
「ひどいな」
「秀吉もわが子に〝捨〟という字をつけたんだよ」
「それもひどいな」
勇気君とサンタ神父は、赤ん坊を風呂に入れた。風呂から上がるとお腹がすいたのか、赤ん坊は20㏄を3回飲み、大きなゲップをした。
孤児院にはあらゆる環境の子どもたちがいたが、孤児たちは世間が考えているほど暗くはない。それぞれ与えられた環境に、悲しんではいられない。感傷に浸れる人間は幸せ者だ。子どもたちにそんな心の余裕はなかった。
孤児院では夕食がすむと、ミサがあった。子どもたちは当番がまわってくると、聖書のなかから好きな言葉を探しだし、その言葉についての感想や意見を述べる。聖書の言葉を読み上げる声は、質素な教会にはふさわしくないほど響きわたるのだった。
サンタ神父は、オルガンが鳴り出すと気持ち良さそうに居眠りを始めたものだ。祭壇の前のろうそくの灯がともされ、朗読が始まる。
空の鳥を見よ、撒きも、刈りも、倉におさめもしないのに……。
……野の百合がどうして育つかを見よ……明日はかまどに投げ入れられる草をさえ……
明日のために心配するな……。
少年の声は、譜面のうえの旋律のようにリズムを刻む。ステンドグラスには、マリア様がいた。左腕にイエスのお尻を抱きかかえ膝の上に立たせている。イエスの右腕は、聖母の胸のあたりにそっと添えられている。オルガンの音色は静かで、鍵盤を打つ指の音さえ聞こえた。
俺なら右腕は胸の上におかず聖母の肩を組むだろうな、そんなに繊細だからイエスははりつけにされてしまったんだ、と考えるころには首が垂れてステオは眠りに落ちていった。
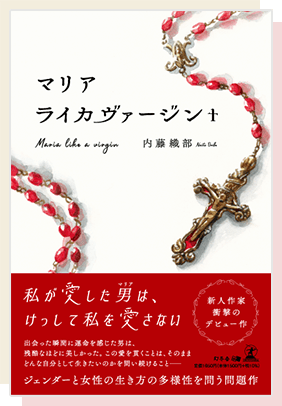
ジェンダーと女性の生き方の多様性を問う問題作
私が愛した男(マリア)は、
けっして私を愛さない
出会った瞬間に運命を感じた男は、残酷なほどに美しかった。
この愛を貫くことは、そのまま
どんな自分として生きたいのかを問い続けること――
<新人作家 衝撃のデビュー作>