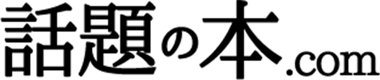マリアの朝は昼だ。みちるがいつ出かけたのかもわからない。
部屋には、いたるところにウイッグがころがっている。ドレッサーの上。淀川長治映画物語のそば。のら7が昼寝している赤い毛布。脱ぎすてられたジーンズのそば。種類もさまざま。金髪のストレート。オレンジのショート。レッドのボブ。ブルネットのウェーブ。カラフルなウイッグはまるで生首のようだ。
外はどしゃぶりの雨。子猫がそれぞれの位置でふやけたウナギのように寝ている。マリアは雨で外に出られない猫たちにブラシをかけてやる。部屋のなかは猫の匂いが立ち込めて、マリアはその香りに満たされる。
みちるの書きかけのレポート用紙の上で、新入りの子猫が寝ている。この子猫はマリアが雨の日曜日、映画を見に行く途中で出くわした。まるで自殺でもするように、走ってくる車の前にちょこんと座っていた。マリアは遠目でそれを見ていた。車は坂道を徐行しながら近づいてくるが子猫は動かない。途方に暮れている。クラクションが鳴っても猫は動かなかった。あーっ、またこれだよ、と思ったときにはマリアは子猫に駆け寄り抱きあげていた。
マリアもみちると同じ習性がある。道を歩けばのら猫に当たる。彼らはマリアと目が合うと、ヤァ、久しぶりだね、と言わんばかりにこちらへすり寄って来る。痩せて骨が浮き出ているのもいれば、艶が良く丸々と太った猫もいた。その猫たちは今ではマリアの部屋を占領している。
拾い上げた子猫は、目やにがたまり、片目がふさがっていた。これでは車が見えるわけがない。猫エイズかもしれないとマリアは映画をあきらめ、家に連れ帰った。
あれから4週間経ち、子猫は元気を取り戻した。鼻水も出て食欲がなかったのでエイズだとばかり思っていたが、医者に連れていき検査をすると、ウイルスの感染による風邪だった。だが、声が出ない。ミャーと泣いているが、こちらには聞こえない。
他の猫たちは外へ出て遊んで帰ってくるが、声なし猫はマリアのそばを離れない。みちるが何度か外へ連れ出したが、置かれた場所から動こうともしないで、みちるが連れ戻しに来るまでじっとそこで待っている。犬のようにみちるの後ろからついて帰ってくる姿は、忠犬ハチ公のようだ。ブラッシングすると、気持ちがいいのかミャーミャーと口を開け閉めしている。鳴いているつもりなのだ。この子は声を失っているのを、知っているのだろうか。
マリアは声なし猫を抱きあげ、譜面にむかった。バンドを結成して25年が過ぎた。今ではリリーしか当時のメンバーはいない。代官山のライブハウスで20時から24時30分まで30分の休憩をとって5回のステージをこなしている。
18歳のときバンドを作り、目黒のライブハウスで活動を始めた。それぞれのパートのクオリティーは低かった。へたくそバンドと影で言われた。マリアはそれなら思いきり爆音を轟かせてやろうと思った。テクニックがないなら、荒削りの音色で自分の未熟さに憤りをこめて、ピックで弦を弾いた。
ピックはすぐにかけ、何度も取り換えた。思うように音色が響かない。気がつくとピックではなく指でつま弾いていた。負けたくない。ギターだけは誰にも負けたくない。指から血が流れるのも構わずマリアはギターをかき鳴らした。屈辱を心に刻みながら。それでも、全員が美しいビジュアル系バンドとして評判になり、雑誌に取り上げられ、少しずつファン層を広げていった。
両サイドをギターで固め、リードギターとサイドギターが交互にサビを奏でる演奏、ベースがジャズのように即興で入り乱れ、ドラムは羽のような柔らかな音からスピード感のあるビートまで叩き上げ、そこへボーカルの楽器のような声が陰影をおとす。「レドメイン」は、ライブをこなすごとに、実力をつけていった。ネアンという曲が、ライブハウスを訪れていたエージェントに目が留まりスカウトされた。メジャーデビューなどともてはやされ、アルバムを9枚出した。
マリアは、作曲はするが詩は作らない。書けないというほうが正しい。小学校の作文コンクールに苦労した。先生は「自分の思ったことや考えていること、将来の夢などを書けばいいのです」というが、言いたいこと、考えている思いが、どう頑張っても10行で書き終えてしまうのだ。マリアにとって大切な想いなんて10行で十分だった。長々書くのは苦手である。詩はリリーが作り、それにマリアが音符をのせていく。
ギターを触っていると頭に浮かんだメロディーを、指がおさえだす。トニックがC・Em・Am、サブドミントがF・Dm、ドミナントがG7。そこへ転調や分数コードをつけ足していく。それらをつなぎ合わせ、ずらしたり、循環させたりしながらバランスを整え、メロディーができる。あとはスタジオミュージシャンとともに何度も手を加え、レコーディングが完成したら、その音源にミックス、マスタリングの作業をおこない、ようやく一曲ができあがる。
ルーティンな日々を繰り返しながらスタジオにこもる生活が半年ほど続く。太陽の光を浴びないメンバーは、全員色白である。徹夜明けなどに廊下をうろついていると、まるでゾンビの集団である。体力は消耗し、アルバムが出来上がるころには、ストレスで体重が激増するか激減しているかのどちらかであった。マリアは難解なコード進行を何度も練習するのが好きだった。ギターが奏でるメロディーは、マリアが唯一現実逃避できる空間だ。
アルバムができると全国ツアーに出た。ファンクラブだけでチケットはソールドアウトになった。一部のファンから火がつき、海外でも人気が出た。それはやがて大波のように広がっていった。海外でのツアーは日本のエージェントほど規制がかからない分、メンバーは羽目を外すこともあった。マリアは浴びるように酒を飲み、毎晩ライブが終わるたびに共演するバンドと酒を酌み交わした。ベッドには気絶する寸前に倒れこんだ。翌日はバスに乗り、次のライブハウスに行く。日本のツアーとは違い、バスでの大陸の移動は過酷なものだった。
対バンとしていろんな国のバンドも参加する。マリアは、自分の好きなバンドの演奏が始まるとステージの脇から眺めた。目の前にあこがれのギタリストがいる。目の前にいてくれるだけでいいのに、ギターを奏でている。
〈なんて美しいフォームでギターを弾くのだろう。遠くを見つめる瞳の先には誰がいるのだろうか〉
その瞳は、ブルーグレー。マリアは嫉妬という厄介な感情を持ち合わせたことがないのだが、陶酔したギタープレーのさなかに彼の心を支配する何者かに、ざわめきを覚えた。音色がマリアの細胞に浸透し、血とともに身体中を駆けめぐる。そんなこともあった。
「レドメイン」のアルバムセールスが最高を記録した年には、武道館でライブを行った。アルバムは音楽評論家たちの評価も高く、自分たちも納得のいく一枚となった。へたくそバンドと陰口を叩かれた日から10年が過ぎていた。人気、曲のクオリティー、テクニック、バンドとしてのボルテージは最高に達した。個々のインタビューも増えその道のスペシャリストのように音楽雑誌は書きたてた。「レドメイン」の世界進出が日本のロックシーンを変えたことは、自他ともに認めざる事実だ。マリアも取材を受けるごとにギターのテクニックを称えられ、プロのミュージシャンからも支持を得た。
武道館ファイナルの日、アンコールの声が渦のようにうねりだした。それを身体中に感じながら、ステージの脇でメンバーと手を重ね合い、気持ちを一つにした。そこまでだ。そこまでがマリアにとっての高揚であった。武道館が終わるとマリアは燃え尽きてしまった。メロディーが出てこない。いや、曲はいくらでも作れる。ノウハウに従って、マリアの技術をもってすれば、いくらでも生産することはできるのだ。けれどそれは、昔のメロディーの焼き直しでしかないのを自分自身が認めざるをえなかった。
マリアは自分にうんざりした。メンバーに「辞めたい」と伝えると、「スランプは誰にでもあるさ」となだめられた。嘘つけ、お前たちも同じ気持ちだろう、とマリアは言いたかった。血肉を注ぎこんだアルバムは、あともう1、2枚が限度であった。プロになるってことは厳しい。自分の限界を、これでもかこれでもかと突きつけられ、認めさせられることなのだ。それでも先に進むことを選ぶ奴が真の玄人なのだ。マリアはプロになることを放棄した。
今では昔の仲間たちがマリアの演奏を聴きにくる。音楽プロデューサー、実家の後継ぎ、ギター教室の先生。それぞれが家庭を持ち子どもを育てている。「うちの息子がさぁ」とやにさがっている顔を見ていると、月日の流れを感じる。マリアのように今でも細々とステージに立っている者はいない。店に来る客は昔からのマリアのファンもいるが、一部の客を除いて、ライブは酒を飲みにくる者たちのBGMにしかすぎない。若いころ、ギターは俺の背骨だ、などと気負っていた自分はどこへ行ったのだろう。今ではただのギター好きの中年。それが現実だった。
マリアは、自分の記憶を紐解いてみた。婆に初めてギターを買ってもらった日、嬉しくて学校をずる休みした。俺の人生の始まりはここからにしよう、と記憶を塗り替えた。孤児院の玄関に捨てられた赤ん坊ではない。〈俺はマリア。俺は捨男ではない。ふざけんじゃねえ〉とこぶしを握りしめ、ギターだけは誰にも負けるまい、と心に焼印を押した。
いったい人間は生まれていつから記憶があるのだろうか、そんなことをマリアは考えていた。リリーは、5歳のとき、両手をグルグル回して空を見ながら歩いていたら電信柱に頭をぶつけた。確かに目から火花が散り、その瞬間から人生が始まったと言っていた。
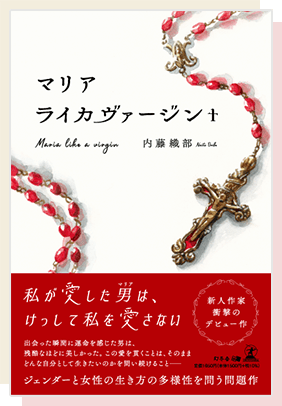
ジェンダーと女性の生き方の多様性を問う問題作
私が愛した男(マリア)は、
けっして私を愛さない
出会った瞬間に運命を感じた男は、残酷なほどに美しかった。
この愛を貫くことは、そのまま
どんな自分として生きたいのかを問い続けること――
<新人作家 衝撃のデビュー作>