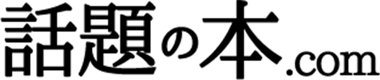暗闇坂に面した家々からは緑がふんだんに溢れている。
古い石垣から葡萄の蔓がメデューサの髪の毛のように、絡まって垂れている。楓の老木は囲いがされ、それを守るようにマンションが建築されている。この街の老木は人間より価値があるようだ。
暗闇坂を上りつめ左に折れると、七福神が祀ってある。みちるは15 円、お賽銭箱に入れた。ジュウブンゴエンガアルヨウニ。15円。これも婆の教えの一つである。
婆には自分流の決めごとがたくさんある。そのなかに、自分の記念日に日の丸をあげることがあった。みちるが初めてこの家を見たときも、国旗があがっていた。憲法記念日でも勤労感謝の日でもないのに。
婆の家は、坂の下の商店街のなかにある。近所に大型複合ビルが建設されて以来、この街に来る観光客が増えた。その一方で、祖父の代からの商店を引き継いでいる者たちのなかには、あっけなく地所を売り飛ばす者もいる。商売を続けるよりテナントとして貸すほうが身入りが多いのか、昔ながらの惣菜屋や酒屋は、ファーストフーズ店やエステサロンに様変わりしようとしていた。
婆の家は、黒塀に冠木門があり、玄関の脇には立派な松の木がある。黒塀から突き出た松の枝は、近代化が進む商店街のなかで異質である。それは映画の書割のようであり、道行く人の目を惹いた。観光客の外国人が写真を撮っているのを見かけることもあった。
その朝、みちるがベランダへ出てみると、5㎝ほどの雪が積もっていた。
みちるは父親に、
「今日は早く家を出たほうがいいよ」
と告げた。
みちるもいつもは大学へ自転車で通学するが、その日は地下鉄にした。
雪が積もった都会はおとなしい。騒音を雪が飲みこんでくれるからだ。みちるは一歩一歩地面を踏みしめながら滑らないように暗闇坂を下りて行った。角のパン屋のおばさんは雪かきに忙しく、みちるに気づかない。季節外れの雪で、商店街の店の前では雪かきをする人たちであふれていた。すっぽり雪で覆われた婆の家から真っ赤な日の丸がはためいていた。
表札には、
家元、
藤原滝野、
藤原捨男、
と、書いてあり、その脇に小さな紙切れで「三味線教えます」とあった。
黒塀の上では白猫がみちるを眺めていた。手を伸ばして触ろうとするとシャーッ、としっぽを立てて怒り、白猫は冠木門の屋根をつたわり家のなかに消えていった。
いつのまにか雪はボタ雪に変わっていた。はためいていた日の丸は、ショボショボと勢いをなくしていった。みちるは、今日は祝日だったかな、と国旗を眺めていたら、
「三味線の入会の方?」
と玄関から出てきた人は、ギターケースを肩から下げているお姉さんのようなお兄さんだった。
このときから、みちるは三味線を習い始めた。
「三味線は音符があってないようなものだからね」
家元は稽古の初日にそう言った。
「まあ、好きなら続くだろうし、これも相性があるからね。それに都々逸は、色っぽいものが多いんだよ。内容がおまえさんには、まだわからないだろうしね」
家元は三味線を取り歌い出した。
末は袂をしぼると知れどぉー
濡れて見たさの夏の雨ぇぇー
声には艶があった。透明で微かにふるえながら、空気のなかに溶けていった。
しばらくみちるは、三味線の稽古に熱心だった。そして、お手伝いの加代さんが風邪でお休みしている間に藤原家の手伝いもするようになった。そのうち三味線の稽古より家元の雑用のほうが多くなり、自然に三味線は弾かなくなった。
みちるは学校が終わるとこの家に来て、お弟子さんたちのお茶やお菓子の用意をして部屋を整える。玄関には季節の花も活ける。それが済むと廊下を拭きあげる。みちるは、この家に初めて来た日、磨き抜かれた廊下の美しさに驚いた。飴色の艶やかな廊下は、家元の肌によく似ていた。
みちるは固く絞った雑巾を4本用意し、台所の入り口から、玄関まで一気に拭き、2本目の雑巾で玄関から台所まで。その往復を2回拭く。仕上げは乾いた柔らかい布に、オリーブ油を染み込ませたもので拭きあげ、最後にから拭きだ。廊下を歩くとまるで自分の影まで映っていそうでお弟子さんたちの白い足袋がキュキュッと廊下に映えた。
その後に夕食の買い出しをして、みちるはひと息つく。マリアが店に出かけると、いつものようにマリアの部屋で音楽を聞いた。何百枚もある数のレコードがキャビネットの中にある。みちるは目を閉じてそのなかの一枚をおみくじのように引く。アコースティックやギターの音色がみちるをすべての悲しみから解き放してくれる。みちるはまどろみながらマリアを想う。目の前に彼がいるときよりも、ずっと彼を感じることができる。
みちるは、この場所にいることが唯一本来の自分になれると感じた。
「家元、私ここにいたい」
と、告げた。
家元は、
「そうかい。それじゃ、しばらく羽を休ませな。お父さんにも了解をとるんだよ。それからうちに住むなら弟子じゃないから私のことは婆とお呼び」
と、言った。マリアはみちるに注文はつけなかったが、自分用にムアツ蒲団を買った。
こうしてみちるはマリアと一緒に暮らし始めた。
三味線の皮は猫。
婆は、いつみちるにこの事実を知らせてやろうかと、考えている。みちるは、野良猫を拾ってきては面倒をかけるからだ。
「婆、お願い。この子、母親とはぐれてしまったみたい。しばらく家においてあげてほしいの。衰弱してかわいそうに。元気になればきっと出て行くと思うからさ。悪性のウイルスにおかされているんだと思うのよ。でも大丈夫。ワクチンあるからさ。あっ、無理ならいいのよ。保健所に連れて行くから。今はね、良い薬があって、死ぬとき、そんなに苦しまないそうよ」
決まりの殺し文句で婆を脅す。
一日でも長生きしてほしいからと、注射、注射と、みちるは騒ぎ立てるが、そのワクチンが猫の細胞と相性が良いとは限らないではないか。どんなに手を尽くしても生物には、与えられた寿命がある。そう考える婆に、「でもデータによるとね」とみちるは力説する。データと結果。すぐこれだ。子どもだましに、婆は呆れかえる。ワクチンをうっても、死んでいく猫を何匹見送ったことか。生物は多少のバイキンとともに生きて行くものなのだ。厳しい人生を生きてきた婆の考え方だ。
婆は、みちるが拾ってきた猫に番号を付ける。みちるは、なぜ名前を付けないのかと抗議した。
3番がゆっくりとこちらに歩いてくる。白に茶のぶちである。この猫は、狸穴公園の花壇のなかで、兄妹とともに捨てられていた。他の3匹は死んでしまったが、この子はスポイトで上手に流動食を食べて回復した。今、彼女のお腹は、ぼこぼことはちきれんばかりだ。婆がバスタオルを畳の上に広げてやると、3番はのろのろと横たわり鼻先をタオルに こすりつけた。5匹は入っているだろう。婆はお腹に手を当ててみた。生温かいものが動 いている。父親はおそらく5番だと婆は睨んでいる。
5番は茶キジで、顔が丸くデブでタンソクだ。婆から見るとタヌキのように見えほほえましい。婆のお気に入りは7番だ。白の毛並みが優雅な顔の小さい猫である。どの猫よりも一日を静かに過ごしている。拾って来たときすでに去勢されていた。そのせいか、メス猫たちにはまったく人気がない。動物の社会では生殖能力が優れているものが、もてはやされるのだ。メスは本能でオスの能力をかぎ分ける。骨格のたくましさ、しっぽの太さ、体臭。それにふてぶしさ。
5番は外から帰ってくると一目散にエサを食べ、水を飲み、廊下の陽だまりに寝る。食器の周りはエサが飛び散り豪快だ。7番は遠くからそれを見ては一瞥を送り、また自分のエサを静かに食べ始める。5番は短い足をおもいっ切り伸ばしあくびをした。抱き上げて頬ずりすると、わかめのような磯の香りがする。メス猫たちはそんな彼を遠巻きに眺める。
彼女たちはマッチ棒のように細く、おとなしい7番には目もくれないのだ。メスにとってどのオスの子孫を残すかは、死活問題である。そのくせ彼女たちは、オスの求愛にはもったいぶる性癖がある。
婆は猫のエサを片付け、水を入れ替えた食器を置いた。水はこまめに入れ替えなければ下痢を起こすからだ。特に暖かい日はなおさらだ。猫たちの朝ご飯がすむと、婆は丁寧に煎茶を淹れ、仏壇に供えた。写真立てのなかには、あの人の顔がある。腕に抱かれた赤ん坊も眠っている。
婆はお茶を一口飲んだ。湯気から立ち上る茶の香りもいつも通りだ。部屋は物音ひとつしない。静けさは追憶を与えてくれる。婆はたっぷりと過ぎ去った時間の恩恵を受けた。
さて、今日も始めるとしよう。お茶を飲み終え、婆は渡り廊下へ向けて声を張った。
「みちるは、大学行ったかい?」
「いないから行ったんじゃないのかなぁ」
マリアも声を返してくる。
「学校は行ってほしいねぇ」
「自分で決めるさ」
あっさりとした返事は彼らしい。
「お前に夢中だからね」
婆が部屋を覗くと、マリアの背中の上で猫が眠っていた。
「お前さんのこと、きっと珍しいんだよ」
婆は、笑った。
「私は新種の生き物か」
マリアは、苦笑した。
男にしては陶器のように毛穴のない肌は、確かに異常に細胞分裂した生物の結果であろう。
「戦時中ならお前はヒコクミンだよ」
「玉砕バンザイ!」
マリアがおどけて両手をあげると、子猫が背から滑り落ちた。
・
マリアが初めて教授を見たのは、みちるが持ってきた写真だった。
「ねぇ、みてこれ。ゆり根ちゃん、教授に気があるのかな、いつもそばにいるんだよね」メイクをしていた顔の前にぬーっと差し出された写真に、何気なく手を止めマリアは覗きこんだ。
そこには数人の女の子に囲まれて男が立っていた。みちるの親友であるゆり根ちゃんも写っている。写真を見た瞬間、マリアの心臓は波打ちだし、頬が熱くなった。やっと砂漠のなかから砂金を探すことができた感覚だ。空港に出迎えられたその男は、学生に取り囲まれ笑顔で、ピースしていた。
「この男、誰?」
訊いてしまった自分に腹が立った。
「岸川教授」
みちるがそう答えると、ミントガムの香りが漂った。
「キョウジュってあのキョウジュ?」
「そう。その教授。なんかインディジョーンズみたいでしょ。ちょっと汚れている感じ、いいよね。ジーンズもビンテージだしさ。あっ、このときハワイから帰ってきたとこでさ、くたびれたアロハシャツ着てるし。ほらこのネックレス見てよ。変わった石、じゃらじゃら首からぶら下げているなんて、クールよね。でもちょっと髪長すぎかな。あと10㎝切ってほしいな」
みちるは、写真の男を指さした。
「あとサングラスも気持ち大きいほうがいいんじゃないか?」
マリアもつられて返答する。
「うん。わかる。わかる。それでさ、もうちょっと角のエッジがきいているほうが、教授の雰囲気だよね」
みちるはマリアの目を見つめた。マリアも見つめ返しながらうなずいた。
感覚というものは、不思議だ。この世に生まれ出るとき、すでに自分の好みというものは確立されている。食べ物の好き嫌いであったり、悲しみの受け取り方だったり、不潔と感じることだったり、他人との距離の取り方だったり。ささいなように見えるが、マリアは感覚を大切なものと考えているのだ。それは美意識と同じだ。
みちるは気が合う妹。生き別れてやっと再会できた兄妹のようだ。きっと男の好みもみちるとは共有できるのだろう。それがマリアの感覚なのだ。そして、マリアは写真に写っている男に懐かしさを覚えた。これはやばいな、と胸のあたりがザワザワしている。マリアの美意識はもう、この男をとらえてしまった。
「何を研究しているんだ?」
「石よ」
「石?」
「地質学者。世界中を、化石求めて歩いているの」
写真のなかで笑っている男は、世界中のどこで暮らしても同じように幸せな顔をして生きていけそうだとマリアは思った。
雷が鳴った。雨音が心地良い。子猫がすっとんでベッドの下へもぐり込んだ。マリアは雷光を見逃してしまった。ヒカリは音よりも速いのだ。愛のように。
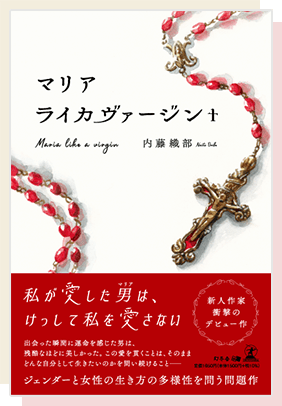
ジェンダーと女性の生き方の多様性を問う問題作
私が愛した男(マリア)は、
けっして私を愛さない
出会った瞬間に運命を感じた男は、残酷なほどに美しかった。
この愛を貫くことは、そのまま
どんな自分として生きたいのかを問い続けること――
<新人作家 衝撃のデビュー作>